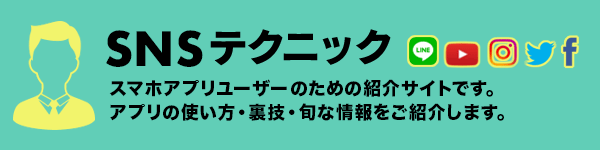Manusとは?
最近、中国で開発されたAI「Manus(マヌス)」が話題になっています。このAIは、ただのチャットボットではなく、人間の指示を受けて自動で作業をこなすAIです。たとえば、以下のようなことができます。
- 「市場のデータを集めて、表にまとめて」と頼むと、データ収集から表の作成まで自動で完了
- 「旅行プランを考えて」と指示すると、日程や観光スポット、ホテルまで提案
- 「ウェブサイトを作って」とお願いすると、実際にサイトを作成
このように、Manusはただの「会話するAI」ではなく、「指示を理解して実際に作業するAI」なのです。
Manusを開発したのは、中国のAI企業 Monica.im(モニカ・アイエム)。2025年3月に発表され、現在は招待制のベータ版が提供されています。このAIは「知識(考えること)と行動(作業)」を結びつけることを目的としており、名前の「Manus」はラテン語で「手」を意味します。つまり、「AIが人間の代わりに手を動かす」ことを象徴しています。

Manusの技術的な特徴
1. AIが自分で計画を立てて作業する
普通のAIは質問に答えたり文章を作成したりするのが得意ですが、Manusは一歩進んで「作業の流れ」を自分で考え、手続きを実行できます。
例えば、「市場のリサーチをしてレポートを作って」と頼むと、以下の流れで進みます。
- インターネットで情報を探す
- 必要なデータを集める
- 情報を整理して文章を書く
- グラフや表を作成する
- すべてをまとめてレポートとして提出
これをすべてAIが自動で行うのが、Manusの最大の特徴です。
2. 外部ツールを使って実作業ができる
Manusは、ただ考えるだけでなく外部のツールを使って作業を実行できます。たとえば…
- Web検索をして情報を収集
- Googleスプレッドシートでデータ整理
- プログラムを書いてコードを実行
- メールを送る
こうした「実際の作業」をこなせるため、「自分で調べてまとめて作業をしてくれるAI」と言えます。
他のAIとどう違う?
1. ChatGPTとの違い
OpenAIのChatGPTは、質問に答えたり文章を作ったりするのが得意です。しかし、Manusは「考えて、実行する」AIなので、単に答えを出すだけでなく、作業をすべてこなしてくれます。
| ChatGPT | Manus | |
|---|---|---|
| 役割 | 会話・情報提供 | 指示を受けて作業 |
| できること | 文章作成・質問応答 | 調査・データ整理・コード作成・レポート作成 |
| ユーザーの負担 | 指示を細かく出す必要がある | ざっくり指示すればAIが自動で進める |
2. Google DeepMindやMicrosoftのAIとの違い
GoogleやMicrosoftもAIを開発していますが、Manusは「自律型AI」として、特に「長い手順をこなす能力」が高いです。現在、GoogleやOpenAIもManusに似た技術を研究していますが、Manusは一足先に実用化されていると言えます。
Manusの課題とリスク
1. 実際に使えるのか?
現在、Manusはベータ版で一部のユーザーしか試せません。そのため、「本当に実用レベルなのか?」という疑問もあります。過去にも「革新的」と言われたAIが実際に使うとイマイチだった例もあるため、期待しすぎるのはまだ早いかもしれません。
2. AIが勝手に動いて大丈夫?
Manusは「考えて、作業を実行」しますが、間違った動作をするリスクもあります。例えば…
- 誤ったデータを集めてしまう
- 余計な作業をしてしまう
- 人間の意図とは違う結果を出してしまう
特に、AIが勝手にコードを実行したり、Webを操作したりできるため、セキュリティ面での慎重な対応が必要です。
まとめ(筆者の感想)
Manusは、AIの新しい可能性を示す画期的なプロダクトです。従来のAIのように「会話する」のではなく、「考えて、実際に作業をする」という点が、未来のAIの形を示唆しています。
一方で、まだ開発段階なので、実際にどれだけの精度で動くのかは不明です。
筆者としては、ManusのようなAIが発展すれば、仕事の効率が大幅に向上する未来が期待できると感じます。ただし、同時に「AIに仕事を任せすぎるリスク」や「安全性」の問題にも注意が必要です。
今後の発展に期待しつつ、冷静に技術の進歩を見守りたいと思います。